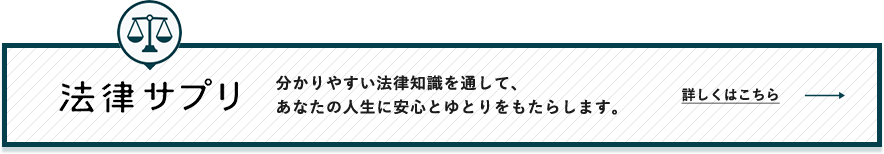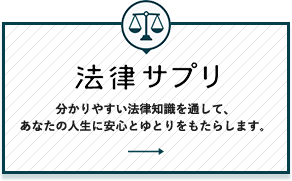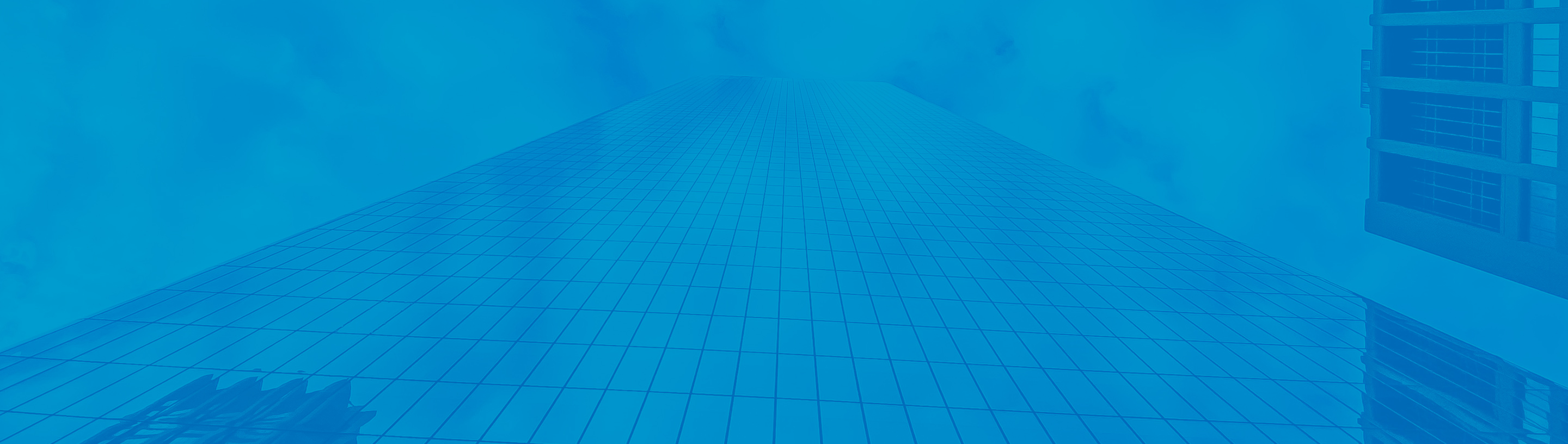債務整理


債務整理
「借金を減らしたい、無くしたい」
「過払い金を取り戻したい」
債務整理過払い金返還請求
なら、すぐにMIRAIOへご相談!
ご相談は無料です
債務整理とは
債務整理とは、借金の減額や、支払期間の調整等により、法的に借金問題を解決するための手続きのことです。
債務整理の手続きでは、まずは利息制限法に基づく引き直し計算を行い借金が減るものがないか、過払い金返還請求ができるものがないかを調査します。
利息制限法に基づく引き直し計算を行ってもなお借金が残る場合には、
『任意整理』を行うか、法的整理(『民事再生(個人再生)』、『自己破産』)を行うかを検討します。
いずれの手段をとるかは、収入と借入金額の関係で決まります。
具体的には、長期分割にすれば収入との関係で支払いが可能な場合には任意整理による解決を、
長期分割にしてもなお返済が困難な場合には法的整理による解決を図ることになります。
どのような手段により解決するのが最適かは、収入、借入金額、その方の資産状況などによって変わってきます。
弁護士が、ご相談者の状況に応じて、最適な解決方法をご提案いたします。
「借金が減らない」、「毎月借金の返済ばかりで貯金が出来ない」、「老後が心配」と一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
早めにご相談いただくことで解決への選択肢が広がります。借金をなくして、さあ、前に進む人生を。

任意整理(和解)
弁護士が借入業者と任意に交渉して、借金を整理する手続です。利息や月々の返済額を減らすことで、現在の支払よりも負担を軽減します。裁判所は通さない手続きです。
民事再生(個人再生)
裁判所に申し立てて借金を減額してもらう手続きです。現在の借金を大幅に減額したうえで、3~5年間の分割払いで返済していきます。一定の条件を満たせば、住宅を残すこともできます。


過払い金とは
過払い金とは「払いすぎた利息」のことです。
「利息制限法」という法律に定められた利息を超えて払った分は、過払い金として貸金業者に返還請求することができます。
まだ借金が残っている場合には、過払い金の分だけ借金を減額することができます。残っている借金よりも過払い金の方が多い場合には、その分の返還請求をすることができます。
借金を完済している場合であっても、完済から10年経っていなければ、過払い金の返還請求をすることができます。

過払い金返還請求
残っている借金よりも過払い金の方が多い場合や、すでに借金を完済している場合には、過払い金の返還請求が可能です。交渉もしくは裁判により返還請求します。
事例紹介
債務整理の事例一覧
すべて
-
CASE STUDY | 0
任意整理(和解)
■事例内容
34歳 サラリーマン 扶養家族:妻(32歳/専業主婦)、子供2人(6歳・5歳) 借金総額:計320万円(消費者金融5社) この方は、子供の将来のために、今の借金生活を改善しなければいけないと考えていました。 しかし、どこに相談すれば良いのか分からず、ただ月日だけが流れ、返済するために借り入れを続けていました。 …
-
CASE STUDY | 0
自己破産
■事例内容
製造業・会社員(42歳)です。 妻、子供2人(中学校・小学校)の4人暮らしです。 5年ほど前から業績悪化に伴い、手取収入が40万円から30万円に下がりました。加えて子供達の教育費も増えていく一方で、家計の不足分を借金で補うようになりました。 はじめのうちは、借金に後ろめたさがありましたが、借入れが増えていくにつれ…
-
CASE STUDY | 0
民事再生(個人再生)
■事例内容
メーカーに勤める、53歳の会社員です。 妻と二人暮らし。子供は独立しており、両親が所有している土地の一部に住宅を建て生活をしています。 当時、自営業を行っていましたが、軌道に乗らず、赤字続きでした。そのため、運転資金の補填に借入れをすることが多くなり、気がつくと借金(住宅ローンは除く)は600万円にのぼっていました…
-
CASE STUDY | 0
過払い金返還請求
■事例内容
64歳 男性 茨城県在住 貸金業者の取引社数 4社…
-
CASE STUDY | 0
自己破産
■事例内容
年金暮らし・67歳、 1人暮らしです。 50代の頃はパート収入もあったため、生活費が不足する時は、よく借金をして賄っていました。その後、年齢も原因してか、パート先を解雇され、生活費に困ったため、以前にもまして借金をするようになりました。 それから、数年が経過して年金を受給するようなりましたが、月手取・13万円ほど…
-
CASE STUDY | 0
任意整理(和解)
■事例内容
44歳 サラリーマン 独身 借金総額:計377万円(消費者金融4社・信販会社1社[キャッシング]) この方は、10年以上前から借入れと返済を繰り返してきましたが、なかなか借金が減りませんでした。…
-
CASE STUDY | 0
自己破産
■事例内容
保守業・会社員(52歳) 妻と義母の3人暮らしです。 独身時代から日常的にパチンコをしており、結婚後もこれを止められず、小遣いでは足りなくなったので借入を始めました。当初はパチンコのために借入をしていましたが、次第に債務返済に追われるようになり、借入と返済を繰り返した結果830万円もの負債を負うこととなりました。…
-
CASE STUDY | 0
過払い金返還請求
■事例内容
48歳 男性 千葉県在住 貸金業者の取引社数 10社…
-
CASE STUDY | 0
民事再生(個人再生)
■事例内容
警備会社に勤務の44歳です。 妻、子供1人(小学生)の3人暮らしで、一戸建て(住宅ローン:残額3,000万円、月返済12万円)に住んでいます。 10年以上前から借入れと返済を繰り返してきましたがなかなか借金が減りませんでした。 借金をした理由は、ITバブル時代に始めた株式投資で徐々に損失を出し、その補填資金を何と…
-
CASE STUDY | 0
過払い金返還請求
■事例内容
60歳 男性 長野県在住 貸金業者の取引社数 3社…
-
CASE STUDY | 0
自己破産
■事例内容
専業主婦(36歳)です。 同居している家族は、夫の両親と子供3人(小学校、幼稚園、乳児)の7人暮らしです。 夫は両親と農業をしており、毎月10万円~30万円の手取収入を得ています。夫の父の持ち家に住んでいるため家賃はかかりませんが、毎月夫が入れてくれる生活費だけでは足りず、6~7年ほど前から借入れをするようになりま…
-
CASE STUDY | 0
民事再生(個人再生)
■事例内容
IT業界に勤務の46歳です。 妻、子供2人(小学生、幼稚園)の4人暮らしで、一戸建て(住宅ローン残額3,000万円、月返済10万円、賞与加算26万円)に住んでいます。 8年程前、昇進したことにより、接待交際費が増加し、接待時の飲食代をクレジットカードで決済していました。 徐々に利用額が増え、収入内で返済ができなく…
-
CASE STUDY | 0
過払い金返還請求
■事例内容
66歳 男性 山梨県在住 貸金業者の取引社数 4社…
-
CASE STUDY | 0
自己破産
■事例内容
自営で運送業をしています。 15年ほど前までは従業員10名ほどの有限会社の代表取締役をしていて、年商3,000万円ほどの売上がありました。 10年前から不況のあおりを受け、取引先が激減し、ついには3年前に事業をたたむことになりました。従業員は全員解雇し、それ以降は私ひとりで、昔の取引先から僅かながらも仕事を回しても…
-
CASE STUDY | 0
過払い金返還請求
■事例内容
59歳 女性 青森県在住 貸金業者の取引社数 4社…
-
CASE STUDY | 0
民事再生(個人再生)
■事例内容
食品会社に勤める会社員、46歳です。 妻と子供2人(高校生・中学生)で生活をしています。 借金をした主な理由は、子供の教育費が一番の理由です。初めは、借入れても何とか返済できるだろうと甘く考えていましたが、次第に借金額が増えていくにつれ、返済が困難となり、最終的には700万円の借金を作ってしまいました。…
-
CASE STUDY | 0
民事再生(個人再生)
■事例内容
商社に勤務の45歳です。 妻、子供1人(小学生)の3人暮らしで、家賃12万円の賃貸マンションに住んでいます。 仕事の立場上、顧客との付き合いや部下へのおごりのための交際費の出費が多くなりました。これらをクレジットカードで決済していたため、徐々に返済額が上がっていきました。 その後、毎月の借金返済のために借入れをす…
-
CASE STUDY | 0
過払い金返還請求
■事例内容
47歳 男性 和歌山県在住 貸金業者の取引社数 4社…
-
CASE STUDY | 0
過払い金返還請求
■事例内容
52歳 男性 茨城県在住 貸金業者の取引社数 8社…
-
CASE STUDY | 0
自己破産
■事例内容
自営業(ガソリンスタンド経営)80歳 妻と2人暮らし バブル崩壊後、資金繰りが苦しくなり、利息が高い商工ローンから借入れを始め、次第に信販会社や消費者金融から借入れをするようになりました。 しかし、売上は減少する一方で、返済は遅れがちになり、とうとう保証人の妻に請求がくるようになりました。また、担保不動産の強制執…
-
CASE STUDY | 0
過払い金返還請求
■事例内容
65歳 男性 東京都在住 貸金業者の取引社数 6社…
-
CASE STUDY | 0
自己破産
■事例内容
小売業・パート(40歳)で、 夫と子供と3人暮らしです。 最初の借入れは、夫の海外転勤や出産等で費用がかさんだためでした。 その後、子供の成長に伴い生活費が増えていく中、扶養控除の範囲内でパートで働き、収入をあまり増やせなかったため、生活費の不足分を借入れで埋めあわせる事が増えていきました。 借金のことは夫に内…
-
CASE STUDY | 0
過払い金返還請求
■事例内容
53歳 男性 青森県在住 貸金業者の取引社数 3社…
-
CASE STUDY | 0
過払い金返還請求
■事例内容
57歳 男性 広島県在住 貸金業者の取引社数 6社…
-
CASE STUDY | 0
自己破産
■事例内容
機械整備業・契約社員28歳、 1人暮らしです。 社会人になったのを機にクレジットカードを作り、それからは、買い物などでよく利用していました。 その後、キャリアアップを考えて転職したのですが、以前よりも給与が減ってしまいました。その後も、転職を数回行いましたが、思うような収入が得られず、以前のクレジットカードでの借…
-
CASE STUDY | 0
自己破産
■事例内容
アルバイト(35歳)です。 夫と中学生の息子の3人暮しです。 息子に喘息の持病があり、その医療費の負担が大きく、夫の収入とアルバイトでどうにか生活を続けていましたが、夫が鬱病で仕事を辞めざるを得なくなり生活費を賄うための借入れを続け、気がついたら借金が200万円近くにまで膨らんでしまいました。…
-
CASE STUDY | 0
自己破産
■事例内容
アルバイト(28歳)で 1人暮らしです。 学生時代から友人に誘われて複数のネットワークビジネスに参加していました。成功者の話を聞いていつかは自分もと思い、自分で商品を買ったり、勉強会に参加したり、そこで出来た知り合いから紹介されていくつもの自己啓発教材も購入したりしているうちに、気がついたら600万円もの借金が出来…
-
CASE STUDY | 0
自己破産
■事例内容
無職・38歳、 1人暮らしです。 以前は派遣社員として収入もあり、その頃は、たまたま手持ち現金がない時に軽い気持ちで消費者金融から借入れをして補填していました。 ある日、突然の派遣契約の打ち切りを言い渡され、その後は失業手当を貰いながらも、再就職活動をしました。なかなか職に就くことが出来ず、ついには無収入となり、…
-
CASE STUDY | 0
任意整理(和解)
■事例内容
34歳 サラリーマン 扶養家族:妻(32歳/専業主婦)、子供1人(10歳) 借金総額:計140万円(消費者金融3社) この方は、借入れをしてすぐに返済できなくなってしまいました。 月々の返済額が少しでも下がれば、裁判手続きをせずに返していきたいと考えていました。…
-
CASE STUDY | 0
自己破産
■事例内容
アルバイト(37歳) 子供2人(小学校・保育園)と3人で暮らしています。 当時、夫の浮気により離婚、母子家庭となりました。 当初は、別れた夫から養育費や慰謝料の支払いがありましたが、徐々に支払われなくなりました。 そのため、昼間と夜間で二つの仕事を掛け持ちしましたが、思うように収入が得られず、借入れに手を出して…
-
CASE STUDY | 0
民事再生(個人再生)
■事例内容
生命保険会社で保険外交員をしている52歳です。 夫と子供2人(専門学生・高校生)の4人で暮らしています。 仕事柄、保険契約をしてもらいたいとの思いもあり、顧客の方に贈り物などをすることが多く、その費用を借入れで賄うことが度々ありました。 その後もそのようなことが続き、気がつくと借金は総額350万円にまで膨らんでい…
-
CASE STUDY | 0
民事再生(個人再生)
■事例内容
サービス業の営業職に就いている44歳です。 妻・子供2人(中3・小5)の4人で一戸建てにて暮らしています。 住宅ローンは1,650万円ほどあり、月返済額は約6万円です。歩合が給与の大半を占めているため、不況になった途端、収入が約半分程度にまで落ち込んでしまいました。 そのため、住宅ローン返済の不足分を賄うために、…
よくあるご質問
いただいたご質問の一部を紹介します。
裁判所にて破産手続きが始まるまでの間は、給料などの差押えを受けることはあります。 ただし、自己破産の裁判が始まった後は差押えができなくなりますし、すでに受けている差押えも必要な手続きを経ることで解消されます。
- 違法な高利での貸付(出資法違反)
- 無登録営業(貸金業法違反:店舗があっても登録業者とは限りません)
- 契約書面や領収書を交付しない(貸金業法違反)
- 帳簿の不備や保管義務違反(貸金業法違反)
- 勤務先や家族に対しても取立や督促を行う(貸金業法違反)
- 内容証明郵便による借入れ業者への警告文書送付
- 監督官庁への苦情申立
- 警察に対する刑事告訴
- 会社へ裁判所からの給料差押え通知が届く。 借入れ業者が差押えの手続きを行うことににより、裁判所が通知を発します。ただし、通常は差押えを回避するように、弁護士が借入れ業者と交渉を行います。
- 官報(国が発行する機関紙)に掲載される。 破産や民事再生(個人再生)の手続きをとられる場合は、その事実が官報に掲載されます。ただし、特殊な業種の企業でない限りは、官報の内容を把握していないのが通常です。
- 会社に対して裁判所から通知が届く 金融機関との間の任意整理であれば問題ありませんが、破産や民事再生(個人再生)手続きする場合には。全ての債権債務について裁判所に申告する必要があります。 その結果、会社との間に貸付け・借入れがある場合には、裁判所から送付される通知などにより、会社が申立の事実を知ることも考えられます。