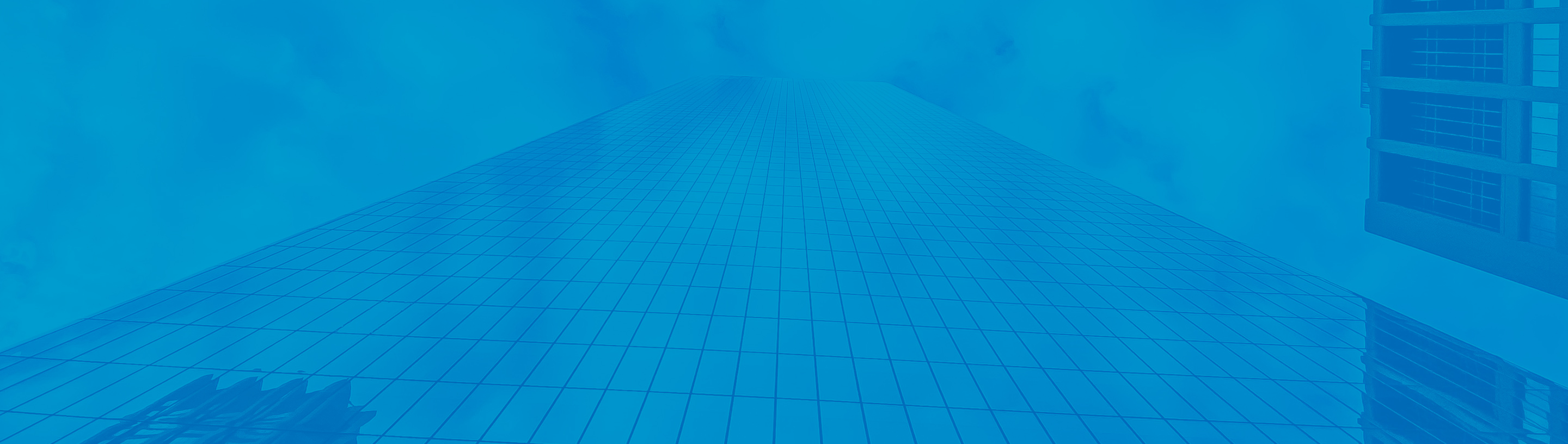後見・財産管理
法定後見制度
裁判所に申立をして、
法定後見人を選任してもらいます。


こんな悩み、
ありませんか?
認知症の妻と二人暮らしだけど、
自分に何かあった時に妻のことが心配
高齢の母が詐欺商法に引っかかって
いるかもしれない。
父が突然、高額な買い物をしてくる。
止められないか。
母が認知症のため、
父の遺産分割が前に進みません。
法定後見制度とは、家庭裁判所に申立をして、認知症などで判断能力が不足した人の法定後見人を選任してもらう制度です。
法定後見人が選任されると、本人だけで一定の行為をすることが制限され、結果的に、資産が散逸することを防ぐことができます。
MIRAIOは、
こう解決します
成年後見人選任申立
判断能力が欠けている人に成年後見人を選任するための手続きです。
保佐人選任申立
判断能力が著しく不十分な人に保佐人を選任するための手続きです。
補助人選任申立
判断能力が不十分な人に補助人を選任するための手続きです。
成年後見制度とは
精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)により、判断能力が欠けているのが通常の状態である人について、家庭裁判所に申立をして、成年後見人を選任してもらいます。
申立は、本人、配偶者、4親等内の親族、検察官などがすることができます。
成年後見人は、本人を代理して契約などの法律行為をすることができ、本人がした不利益な法律行為を取り消すことができます。
ただし、日常生活に関する行為(日用品の購入など)については取り消すことができません。
保佐制度とは
精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)により、判断能力が著しく不十分な人について、家庭裁判所に申立をして、保佐人を選任してもらいます。
申立は、本人、配偶者、4親等内の親族、検察官などがすることができます。
保佐人が選任されると、本人は次の行為について、保佐人の同意なくしてできなくなります。
保佐人の同意を得ないでした行為は、本人か保佐人が取り消すことができます。
ただし、日常生活に関する行為(日用品の購入など)については取り消すことができません。
◆保佐人の同意が必要な行為
1 貸したお金の元本の返済を受けたり、利用すること
2 金銭を借り入れたり、保証人になること
3 不動産などの重要な財産の売買など
4 訴訟の原告になること
5 贈与、和解・仲裁契約
6 相続の承認、相続放棄、遺産分割
7 贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件の付いた贈与・遺贈を受け入れること
8 建物の新築、改築、大修繕
9 一定の期間を超える賃貸借契約
補助制度とは
精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)により、判断能力が不十分な人について、家庭裁判所に申立をして、補助人を選任してもらいます。
申立は、本人、配偶者、4親等内の親族、検察官などがすることができます。
補助人が選任されると、本人は「保佐人の同意が必要な行為」の一部について、補助人の同意なくしてできなくなります。
補助人の同意を得ないでした一定の行為は、本人か補助人が取り消すことができます。
ただし、日常生活に関する行為(日用品の購入など)については取り消すことができません。
解決までの流れ
後見・財産管理の解決までをサポートします。
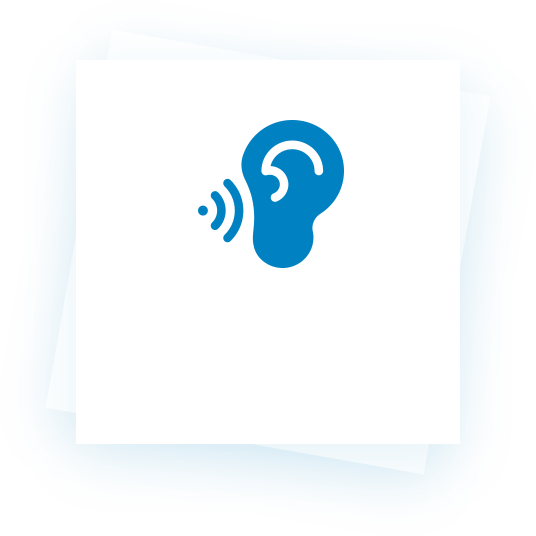
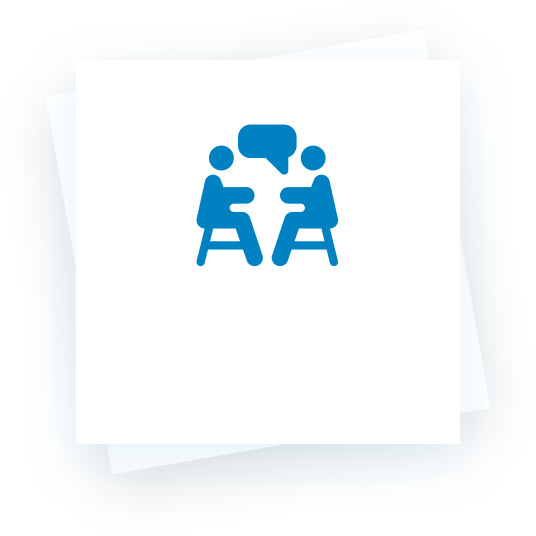
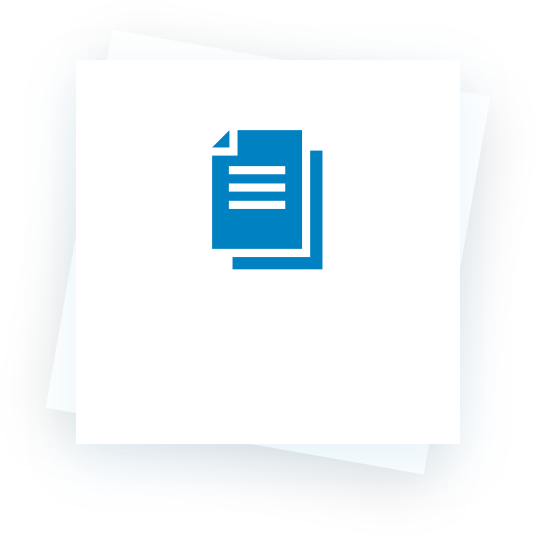
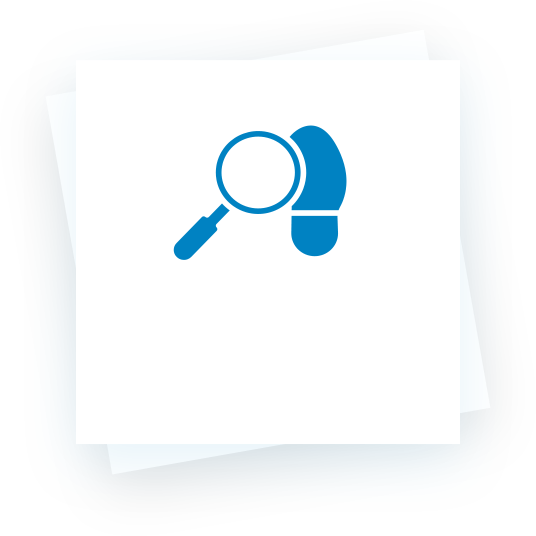

事例紹介
法定後見制度の事例一覧
-
CASE STUDY | 0
法定後見制度
■事例内容
私は、認知症の妻と二入暮らしです。自分もこの先、高齢で衰えた場合、また妻より先に逝った場合、認知症の妻の世話や施設入所、財産管理などをどうすればよいか悩んでいます。…
-
CASE STUDY | 0
法定後見制度
■事例内容
父が亡くなり、相続人間で遺産分割の協議をすることになりましたが、母親が認知症では遺産分割協議はできないといわれました。預貯金の相続手続きでも母が単独で行為することは困難です。家族では代理人となれないので、何か良い方法を教えてください。…
法定後見制度に関するよくあるご質問
法定後見制度について、いただいたご質問を紹介します。
- 職業や資格の制限 他人の財産を管理する職業に就くこと(取締役、監査役等)、専門の資格取得(医師、弁護士、税理士等)、免許・登録が必要な職業に就くこと(投資顧問業、警備業、古物営業、旅行業等)などについては制限されます。
- 選挙権・被選挙権の制限
- その他 印鑑の登録ができません。すでに登録しているものは抹消されます。